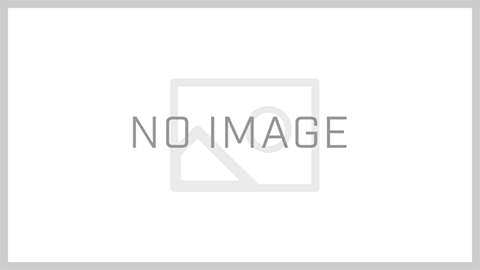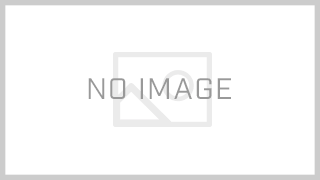「〇〇だからしょうがない」が口癖の人とうまくやっていくには
福祉現場で9年間従事してきた専門家が、行動学・心理学の視点から「〇〇だからしょうがない」が口癖の人への効果的な対応方法を解説します。知的障害者施設(4年)、生活保護ケースワーカー(4年)、子ども家庭支援センター(1年)での実務経験に基づいた実践的なアプローチをお伝えします。
こんな言葉、聞いたことありませんか?
「病気だからしょうがない」
「障害があるから俺にはわからねえ」
「年だからわたしにはできないよ」
「僕、発達障害だから人の気持ちがわからないんだよね」
福祉現場で9年間働く中で、私はこうした「〇〇だからしょうがない」という言葉を数え切れないほど聞いてきました。最初は「何を言っているんだ、この人は」と戸惑うこともありましたが、行動学と心理学を学ぶにつれて、この言葉の背景にある深い理由が見えてきました。
今日は、そんな人たちとどう向き合い、どう支援していけばよいのかを、専門的な知識と実務経験を交えてお話しします。
なぜ「〇〇だからできない」と言うのか? – 行動学的分析
行動獲得のメカニズム
行動学の父と呼ばれるB.F.スキナーは、人間の行動がどのように形成されるかを研究しました。彼の理論によると、私たちの行動は「行動→結果」のサイクルによって強化されます。
具体例:動物の学習行動
- • 木を登る → おいしい実が手に入る → また木を登る
- • 夜に行動 → 肉食獣に襲われない → 夜の行動が増える
- • 大きな声 → 仲間が集まる → 大きな声を出す頻度が増える
では、「〇〇だからできない」と言う人の場合はどうでしょうか?
✓ 優しい言葉をかけてもらえる
✓ 難しい課題を免除してもらえる
✓ 嫌いなことを避けられる
✓ 注目を集められる
専門家の視点
この言葉は「打ち出の小槌」のような働きをしています。振れば望ましい結果が得られるため、無意識のうちに使用頻度が増加してしまうのです。これは決して悪意からではなく、人間の自然な学習メカニズムなのです。
心の奥にある不安 – 心理学的解釈
アイデンティティの混乱と不安
「〇〇だからできない」と言う人の多くは、実は深い不安を抱えています。障害や病気、年齢などの要因で繰り返し失敗体験をしてきた結果、「自分は何者なのか」がわからなくなってしまうのです。
心の動きの流れ
繰り返される失敗体験
「なぜ失敗するのか」がわからない不安
自分にラベルを貼って安心を求める
「病気だから」「障害だから」という言葉に依存
ボウルビィの愛着理論と安全基地
心理学者ジョン・ボウルビィは、人間が健全に成長するためには「安全基地」が必要だと提唱しました。安全基地とは、心理的に安心できる存在や環境のことです。
安全基地の機能
- • 失敗しても受け入れてもらえる安心感
- • 新しいことに挑戦する勇気の源
- • 自己肯定感の土台
- • ストレス時の避難場所
実務経験からの洞察
生活保護ケースワーカーとして働いていた4年間で、多くの相談者が「安全基地」を失っている状況を目の当たりにしました。家族や友人からの理解を得られず、社会からも孤立してしまった結果、病気や障害という「わかりやすい理由」にしがみつくしかなくなっているのです。
効果的な対応方法 – 実践編
基本原則:否定しない、受け入れる
避けるべき対応
- • 「そんなことない」と否定する
- • 「甘えている」と責める
- • 無理やり行動させようとする
- • 説教や正論で説得する
推奨される対応
- • 「そうなんですね」と受け止める
- • 「そんな方法もあるのか」と関心を示す
- • 「そりゃ面白い」と肯定的に反応
- • 感情に共感を示す
段階的アプローチ
第1段階:信頼関係の構築
まずは安全基地として機能できるよう、信頼関係を築きます。批判や否定を一切行わず、相手の感情や体験を受け入れる姿勢を示します。
具体的な言葉かけ例
- • 「大変だったんですね」
- • 「そういう見方もありますね」
- • 「教えてくれてありがとうございます」
第2段階:小さな成功体験の積み重ね
信頼関係ができたら、できることから少しずつ挑戦してもらいます。失敗しても受け入れられるという安心感の中で、新しい体験を促します。
知的障害者施設での実例
「僕はダメな人間だから」と言っていた利用者さんに、まずは毎日の挨拶から始めてもらいました。「おはようございます、〇〇さん!」と私から声をかけ続けることで、徐々に自分からも挨拶をしてくれるようになりました。
第3段階:自己効力感の向上
小さな成功を積み重ねることで、「自分にもできることがある」という感覚を育てます。この段階では、「〇〇だからできない」という言葉の頻度が自然と減ってきます。
現場で使える実践テクニック
コミュニケーション技法
1. リフレクション
相手の言葉を繰り返し、理解していることを示す
あなた:「人の気持ちを理解するのが難しいと感じているんですね」
2. 部分的同意
全面否定せず、理解できる部分を認める
自己保護の重要性
適切な距離感の維持
- • 支援者自身の精神的健康を優先
- • 必要に応じて他の専門家に相談
- • 一人で抱え込まない
境界線の設定
- • できることとできないことを明確にする
- • 責任の範囲を相手と共有する
- • 感情的に巻き込まれすぎない
重要な注意点
子ども家庭支援センターでの経験から学んだことですが、支援者が燃え尽きてしまっては意味がありません。「この人を変えてあげなければ」という使命感は時として危険です。
相手のペースを尊重し、長期的な視点を持って関わることが大切です。すぐに変化が見られなくても、それは失敗ではありません。
まとめ
理解すべき3つのポイント
- 1. 行動には必ず理由がある
「〇〇だからできない」という言葉は、過去の学習の結果として獲得された行動パターンです。 - 2. 心の奥には不安がある
この言葉の背景には、自分自身への不安や混乱があります。 - 3. 安全基地が回復のカギ
信頼できる関係性の中でこそ、人は変化への勇気を持てるのです。
実践での心構え
- • 否定しない – まずは相手の言葉を受け止める
- • 焦らない – 変化には時間がかかることを理解する
- • 自分を守る – 適切な距離感を保つ
- • 小さな変化を見逃さない – 些細な進歩も認める
福祉の現場で学んだ最も大切なことは、「人は必ず変わることができる」ということです。しかし、それには時間と適切な環境、そして何より理解してくれる人の存在が不可欠です。
この記事が、身近にそうした方がいらっしゃる皆さんの一助となれば幸いです。世の中には様々な人がいますが、誰もがそうなってしまう可能性があります。お互いに理解し合い、支え合える社会を作っていきましょう。