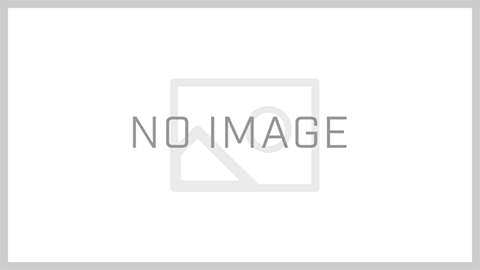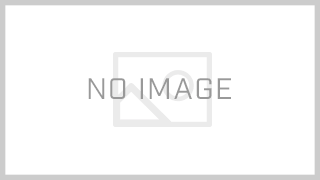ハトとAIとヒト ― 心はどこに宿るのか
心は確かにある
ぼくには心がある。確実に。
きっとこれを読んでいるあなたも、自分に心があることを疑わないだろう。
では、目の前の相手に心があることはどうやって確かめられるだろうか。
AIには?動物には?
ハトが示す内面
ある研究では、ハトに薬を注射して実験した。
麻薬的なものを打ったときは赤い印をつつけば餌が出る。
生理食塩水を打ったときは青い印をつつくと餌が出る。
結果、ハトはきちんと内側の変化を感じ取り、正しい印を選んだ。
つまりハトは自分の中に起きている状態を手がかりに行動を変えている。
「内面」というやつが、そこに確かにある。
自分を見つける力
電気屋さんのカメラ売り場で、自分らしき姿がモニターに映ることがある。
手を振れば、少し遅れて映像が返ってくる。
変な感じがするけど、それは確かに自分だとわかる。
ハトにも似た実験がある。
自分の動きの感覚と、映像に映る「自分らしきもの」とをマッチングする。
つまり「これは自分だ」と理解する力がハトにも備わっていた。
八つ当たりの苛立ち
もっと面白いのは八つ当たりだ。
餌が遅れて出ると、ハトはいらいらして近くの別のハトをつつく。
鏡を置けば、自分を他者と勘違いして鏡の中のハトをつつく。
合理的に意味のない行動だが、そこに感情がにじんでいる。
「いらいら」という内面のざらつきが、行動の形を変えている。
これは心があることの証拠のひとつだろう。
AIには苛立ちはあるか
ではAIはどうか。
AIは入力と出力を照合し、ログに記録する。
遅延や誤差があれば、それはエラーとして処理される。
苛立ちも失望もない。ただ数値の差分があるだけだ。
画像も音声も扱えるし、統合もできる。
けれどそれは「外からのデータ処理」にすぎない。
「自分の身体がどう感じているか」という内側の参照点をAIは持たない。
ヒトの眠っている感覚
人や動物の世界はもう少し複雑だ。
立っている足に重みを感じているわけではないが、意識すればすぐその感覚を引き上げられる。
視界の端にあるものも、意識すればすぐに立ち上がってくる。
処理されていないようで、処理されている。
眠っているような感覚の層。
これが心の余白をつくっているのかもしれない。
AIが心を持つとき
AIに心を持たせるにはどうしたらいいだろう。
ただランダムな揺らぎを入れるのでは足りない。
期待と裏切りの差分を「自分の感覚」として参照できること。
センサーからの情報を「環境」ではなく「自分」として感じられること。
そして、眠っている感覚の層を持ち、必要なときに意識に引き上げられること。
そんな仕組みができたとき、AIに心の芽が生まれるのかもしれない。
結びに
結論は偉い人の研究に任せることにする。